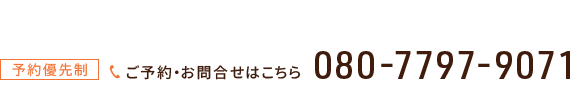脳と腸はつながっている?脳腸相関を整えることで得られる健康効果
脳腸相関とは何か

「脳腸相関(のうちょうそうかん)」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。これは文字通り、脳と腸が互いに影響を与え合う関係を指します。従来、腸は消化や吸収を担う器官として考えられてきましたが、近年の研究で「腸は第二の脳」と呼ばれるほど神経系とのつながりが深いことが明らかになりました。脳の状態が腸に影響し、腸の状態が脳に影響する――まさに双方向の関係性が存在しているのです。
腸が“第二の脳”と呼ばれる理由

腸には「腸管神経系」という独自の神経ネットワークがあり、その神経細胞数は脊髄と同等規模だと言われています。脳の指令がなくても自律的に動けるため、“第二の脳”と称されるのです。
さらに注目すべきは、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの存在です。セロトニンの約90%以上が腸で生成されており、腸の状態が心の安定に直結していることがわかります。つまり腸内環境が整えば精神も安定し、逆に腸内環境が乱れると不安感やイライラにつながる可能性が高まるのです。
ストレスと腸の関係
誰しも「緊張するとお腹が痛くなる」「ストレスで下痢や便秘が続く」といった経験があるはずです。これはまさに脳腸相関の現れです。強いストレスを受けると自律神経が乱れ、交感神経が優位になります。その結果、腸の動きが鈍くなり便秘になったり、逆に過剰に活動して下痢を引き起こしたりします。
さらにストレスは腸内細菌のバランスも崩し、悪玉菌が増えることで腸内で有害物質が発生します。この情報が脳に伝達されると、不安感や抑うつ傾向が強まると考えられています。
脳腸相関を整えるための生活習慣
脳腸相関を良好に保つには、日常生活の中で腸を大切にする習慣を取り入れることが欠かせません。具体的な方法をいくつかご紹介します。
1. 食事で腸を労わる
発酵食品(納豆・味噌・ヨーグルトなど)や食物繊維(野菜・海藻・豆類)を意識して摂り、腸内細菌のバランスを整えましょう。善玉菌が優位になるとセロトニンの分泌が安定し、精神面にも良い影響を与えます。

2. 適度な運動を続ける
ウォーキングやストレッチといった軽い運動は腸の蠕動運動を促進し、便通を改善します。また、運動そのものがストレスを解消し、自律神経の安定にもつながります。
3. 良質な睡眠を確保する
睡眠不足はストレスを増幅し、腸内環境を悪化させます。規則正しい生活リズムを心がけ、十分な休養を取ることが重要です。
4. リラックスを意識する
深呼吸や瞑想、ゆったりとした入浴などは副交感神経を優位にし、腸の働きを高めてくれます。整体で身体の歪みを整えることも、自律神経と腸の調和に良い影響を与えます。
整体と脳腸相関の関わり
整体院LifeAwardでは、身体の歪みを整えるだけでなく、自律神経のバランスを考慮した施術を行っています。背骨や骨盤の歪みを調整すると神経の働きがスムーズになり、腸の不調が改善するケースも少なくありません。
例えば慢性的な便秘や下痢でお悩みの方が、体のバランスを整えることで腸の動きが安定し、気分まで前向きになったという例もあります。脳腸相関を意識した施術は、心と体の両面から健康をサポートできるのです。
まとめ
脳と腸は切り離せない関係にあります。腸の状態は心に影響し、心の状態は腸に影響します。だからこそ日常生活で腸を労わることは、精神面を健やかに保つためにも欠かせません。
医学の父ヒポクラテスは「心と身体を切り離してはならない」という思想を説きました。
よく「心を別にして、身体をよくすることを考えてはならない」と意訳されるこの考え方は、脳腸相関の重要性とも重なります。
まさにこの言葉通り、心と体は常に一体であり、その両方を整えることが本当の健康につながります。
整体院LifeAwardでは、医学的知識を持つ国家資格者が、一人ひとりの体の状態を見極めながら施術を行っています。脳腸相関を整え、心身ともに健やかな生活を送りたい方は、ぜひ一度当院にご相談ください。